「水を注ぐ、靴を揃える…その一つひとつが成長のチャンス!」
毎日の生活の中で、子どもが自分で水を注いだり、靴を揃えたりする姿を見ると、思わず微笑んでしまいますよね。
でも、これらの一見当たり前の動作には、実は 子どもの成長を支える大切な学び が隠れています。
モンテッソーリ教育では、こうした日常生活の動作を「おしごと」と呼び、子どもが自立心や集中力、手先の器用さ、社会性を育むための活動として大切にしています。
この記事では、現役の幼稚園教諭が ”家庭でもできるモンテッソーリ教育の ”日常生活の練習(Practical Life)” について、具体的な活動例や年齢別の進め方、取り入れるときのポイントまで詳しく解説します。
- モンテッソーリ教育の基本
- 日常生活の練習とは?
- 年齢別の具体的な活動例
- 家庭で取り入れるポイント
- 日常生活の練習が育む力
モンテッソーリ教育と”日常生活の練習”
モンテッソーリ教育は、イタリアの医師であり教育者でもある マリア・モンテッソーリ によって提唱された教育法です。
この教育法の大きな特徴は、「子どもには、自分を成長させる力がもともと備わっている」という考え方にあります。
大人はその力を信じ、子どもが自ら学び、自分のペースで成長できるように 環境を整え、集中して活動できる時間を大切にする ことが求められます。
世界中で支持されているモンテッソーリ教育では、子どもの 自立心や主体性 を育むことを最重要視しています。その中でも、特に0歳〜6歳の幼児期に欠かせない活動が 「日常生活の練習(Practical Life)」 です。
モンテッソーリ教育で育つ自立心と集中力”日常生活の練習”とは?
「日常生活の練習(Practical Life)」とは、食事の準備や掃除、着替え、道具の扱いなど、大人にとっては当たり前の動作を、子どもが自分の手でできるようになるための活動です。
モンテッソーリ教育では、生活の中にある動きを「学びの素材」として大切にします。
たとえば…
- 水をコップに注ぐ
- ボタンをとめる
- 箒で床を掃く
- 靴をそろえる
こうした動作は単なる「お手伝い」ではなく、子どもの手と脳を育てる「知的な活動」そのもの。
モンテッソーリ教育の核となる大切な要素です。
園で子どもたちを見ていると、「水を注ぐ」や「雑巾を絞る」といった活動に、驚くほど集中して取り組む姿が見られます。
大人からすると“ただの作業”に見えるかもしれませんが、子どもにとっては自分の体を使って工夫する大切な練習なんですね^^
4つの柱でとらえる日常生活の練習
1.基本的な生活習慣
- 手を洗う
- 着替える
- 靴を履く・脱ぐ
- ハンカチで鼻をかむ→ 自分の身の回りのことを自分で行う「自立の第一歩」
2.環境を整える活動
- お花を生ける
- 床をほうきで掃く
- テーブルを拭く
- 食器を並べる→ 環境を大切にする心や秩序感が育ちます。
3.他者との関わり方
- 順番を待つ
- 「どうぞ」「ありがとう」など言葉で伝える
- 相手の話を最後まで聞く→社会性や礼儀を学ぶ機会になります。
4.動作の正確さと集中力
- 水をこぼさずに注ぐ
- 洗濯ばさみを使う
- ビーズをひもに通す→ 手先の巧緻性が育ち、のちの文字を書く・道具を使う基礎につながります。
「どうぞ」「ありがとう」といった言葉のやり取りは、年少さんのうちから少しずつ身につきます。
園では繰り返し伝えることで習慣になっていきますが、お家でも同じ姿勢を見せてもらえると、定着がぐっと早まりますよ。
なぜ大切?”日常生活の練習”のねらい
この分野の大きな目的は、次の2つに整理できます。
① 運動の完成
自分の意志どおりに体を動かせることは、学びのすべての基盤。
粗大運動(体幹や腕の動き)と微細運動(指先や手首の動き)の両方を整えることができます。
② 自立心・独立心の育成
「できた!」という体験は、子どもの自己肯定感を育てます。
さらに、理解力・集中力・行動力・社会性など、心の成長にもつながります。
具体的な活動例(年齢別)
モンテッソーリ教育では、子どもの発達段階に合わせて日常生活の練習を提供することが大切です。
年齢によって活動内容や難易度を調整することで、無理なく自分の力で取り組んでいくことができますよ。
幼児前期(1〜3歳)
この時期は、主に 動きそのものを楽しむこと が中心です。
小さな手で物をつかみ、移動させるなど、基本的な動作を通して手先の器用さや集中力を養います。
- スプーンやトングで物を移す
- 洗濯ばさみで物をつまむ
- 小さな水差しで水を注ぐ
- 雑巾を半分に折る
幼児後期(4~6歳)
後期になると、前期で身につけた動作を より正確に、洗練された形で行うこと が求められます。
細かな調整力や順序を守る力、丁寧さが育つ活動に取り組んでいきましょう。
- 洗濯物をたたむ
- 靴磨き
- 簡単なサラダ作り(野菜をちぎるなど)
- 植物の水やりやお世話
年齢に応じた活動の進め方
子どもの発達には「運動の敏感期」があり、前半と後半で活動の提供の仕方が異なります。
・前半(0〜3歳頃)
この時期は、動きそのものを習得する段階です。
座る・立つ・持つ・貼る・すくうといった基本的な身体動作を楽しむことが中心になります。
大人は手順よりも、動作を楽しむ環境を整えてあげることが大切です。
・後半(3~6歳頃)
習得した動きを調整し、より正確で洗練された形に発展させる時期です。
たとえば、台紙の形にぴったり貼る、決まった位置に物を置く、雑巾をなめらかに拭くといった細やかな作業を取り入れます。
こうした活動を通して、集中力・秩序感・手先の精密さがさらに育まれます。
前半(0〜3歳)は“やってみたい!”という気持ちを大切に、後半(3歳〜6歳)は“できた!”という成功体験を重ねることが成長の鍵です
家庭で日常生活の練習を取り入れるポイント
モンテッソーリ教育の「日常生活の練習」は、家庭でも無理なく取り入れることができます。ここでは、家庭で実践する際の具体的なポイントをご紹介します。
1.子どもサイズの道具を用意する
小さな手でも扱いやすいピッチャーや子ども用ほうきなど、 子どもに合った道具を用意すること が大切です。
使いやすさは成功体験につながり、子どもの自信ややる気を引き出します。
2.失敗も経験の一部として受け止める
水をこぼしたり、順番を間違えたりすることもありますが、 叱らずに見守ることが成長につながります。
失敗も学びの一部として経験させることで、子どもは自分で考え、工夫する力を育みます。
3.「やらせてあげる」のではなく「任せる」気持ちで見守る
大人が手を出してしまうと、子どもは挑戦する機会を失ってしまいます。
- まずは大人が ゆっくり・無言で動作を見せる(提示)
- 次に子どもに 自由にやらせてみる
- 最後に 見守る
「提示 → 自由にやらせてみる → 見守る」の流れが基本です!
介入は最小限にし、子どもが自分でできたときの喜びや達成感をしっかり認めてあげてくださいね^^
4.安全な範囲で自由に遊ばせる
自分で道具や作業を選べる環境を整えることもポイントです。
自由に選択できることで、 主体性や判断力 が育ちます。安全面に注意しつつ、できるだけ子どもに任せることが大切です。
お子さんが小さな成功体験を重ねることが、自立心や集中力を育てる最大のコツです。
ご家庭でもこの考え方を意識すれば、日常生活の練習が自然に生活の一部となり、子どもの成長をサポートすることができます!
まとめ:家庭でもできる日常生活の練習
モンテッソーリ教育における 日常生活の練習(Practical Life) は、子どもの成長を支える、立派な学びの活動です。
ご家庭でのちょっとした関わりや見守りが、お子さんの 集中力・自立心・運動能力 をぐんと伸ばすきっかけになります。
日常生活の練習を通して、子ども達は自分で考え、行動し、成功体験を重ねることができます。
この体験が 「自分でできた!」という自信 につながり、主体性や社会性、感性といったさまざまな力を育みます。
ご家庭でも、身近な生活動作 — 例えば水を注ぐ、靴を揃える、道具を扱う—を意識して取り入れるだけで、お子さんの成長を自然にサポートできます。
幼稚園教諭として日々感じるのは、
「子どもが自分の力で挑戦し、達成感を味わう瞬間こそが、成長の土台になる」
ということです。
家庭でもこの考えを意識して、子どもが自由に取り組める環境を整え、見守りながら支援してあげることが大切です。
日常生活の練習は、運動能力や自立性だけでなく、集中力・社会性・感性といった 子どもの心と体の基盤 を築く活動です。小さな成功体験を一緒に喜びながら、家庭でも積極的に取り入れてみてくださいね。
お子さんと一緒に「できた!」を楽しむことこそ、
モンテッソーリ教育をご家庭で実践する一番の方法です^^
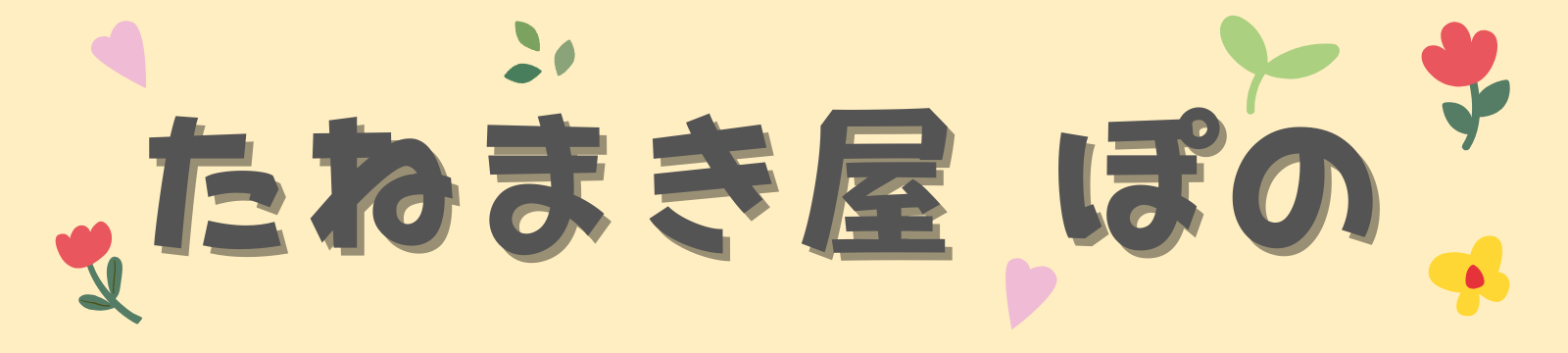
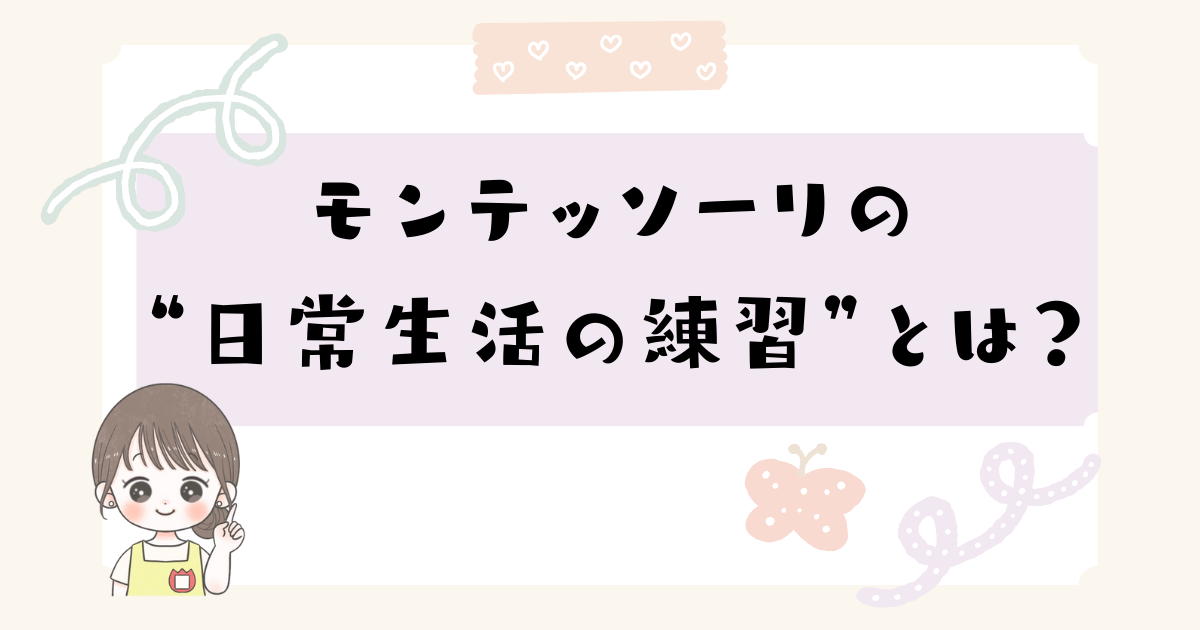
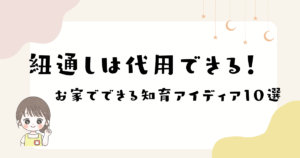
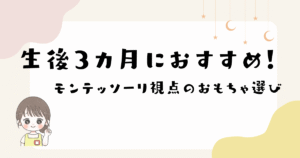
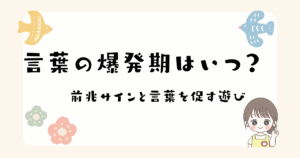
コメント